Women's History Monthに考える:女性の自己決定権とリプロダクティブライツ
ー3月はWomen's History Monthー
権利を勝ち取ってくれた先人の女性たちに感謝するとともに、いまだ解決されていない課題にも目を向ける大切な機会です。
図書館で出会ったWomen's History Monthの本と映画
最近、図書館に行くのが好きなのですが、今月はWomen's History Monthということで、専用のコーナーが作られていました。
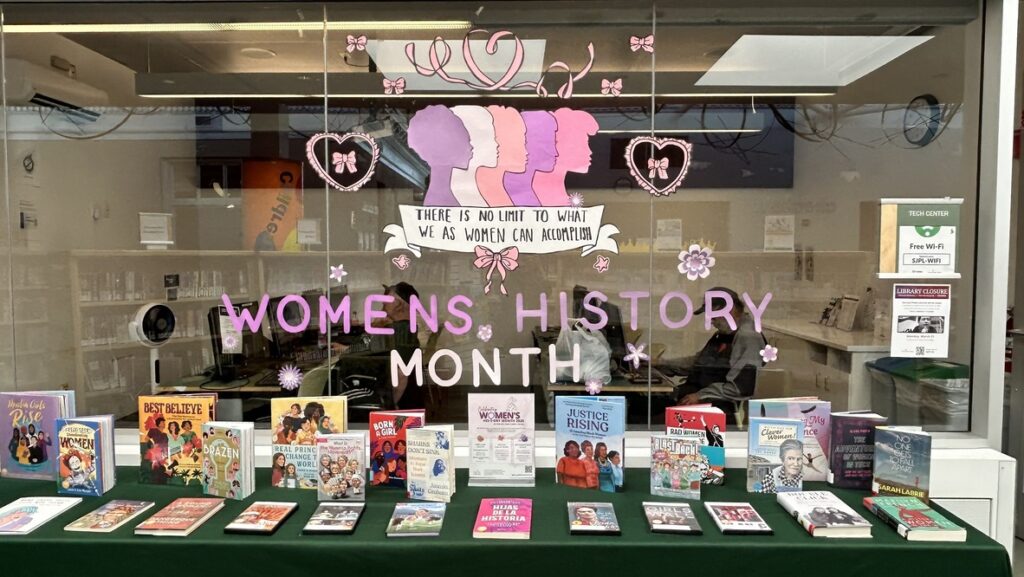
以下のような本や映画を読了・視聴しました。
活躍する女性たち
・Brazen: Rebel Ladies Who Rocked the World
・Girls Who Run the World: 31 CEOs Who Mean Business
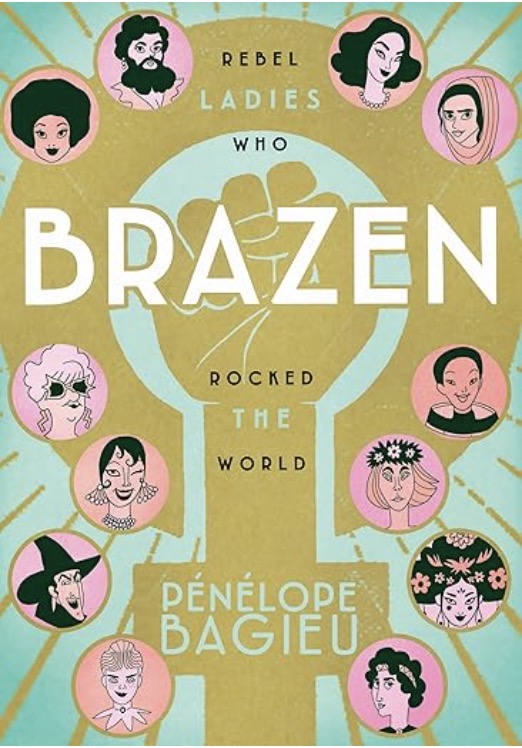
ジェンダー不平等について
・What Makes Girls Sick and Tired
ルース・べイダー・ギンズバーグ判事
・On the Basis of SEX(映画)
・RBG(ドキュメンタリー)
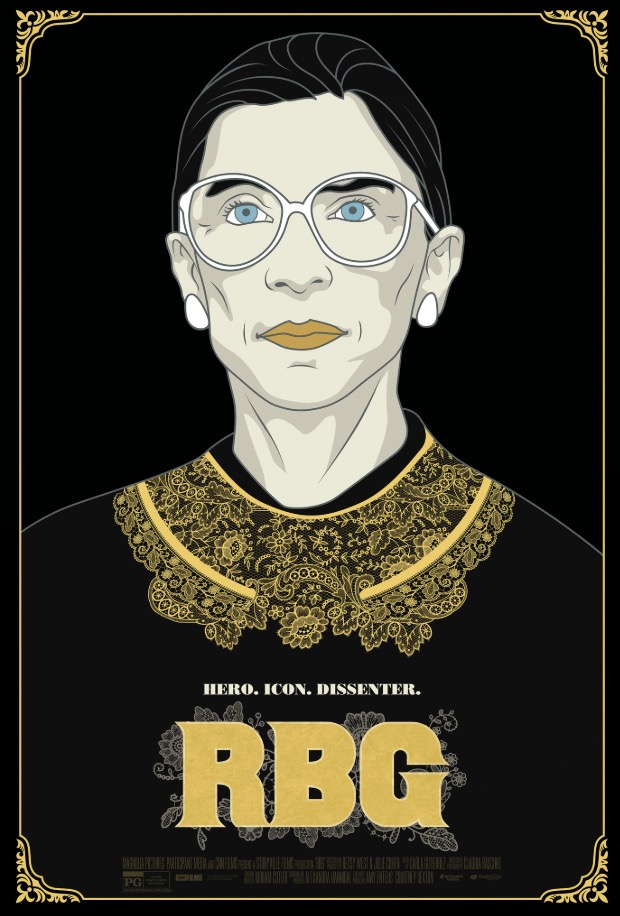
女性の中絶の権利について
・Reversing Roe(Netflix・ドキュメンタリー)
・PLAN C(ドキュメンタリー)
これらの作品を通じてさまざまなことを考えましたが、特に女性の自己決定権とリプロダクティブライツについて書いていこうと思います。
自分の人生を決めるのは自分なのに
もちろん女性には「結婚するか、しないか」「産むか、産まないか」「いつ産むか」を決める権利があります。
しかし、実際には社会がこれを管理したりジャッジすることが少なくありません。
男性にも当然あるでしょうが、女性の方がより厳しく評価されると感じてきました。
結婚・出産・育児のプレッシャー
「結婚して、子どもを育てて一人前」 「女性の幸せは結婚して子どもを産むこと」
こうした価値観が、女性のライフプランの自由を奪い、結婚や子供を産まない女性を生きにくくさせています。
文化とメディアが映し出す価値観
映画『東京物語』ー1953年 小津安二郎
この作品では、結婚や家庭を持つことが女性の役割として暗黙のうちに期待されている様子が描かれています。戦後日本の社会背景の中で、未婚の女性が家族にとって「片付けるべき存在」として扱われることがありました。女性が結婚することで家族の責任から解放される、という考え方が反映されています。
小説『コンビニ人間』ー2017年 村田沙耶香
正社員や結婚して子どもを産むことが「人としてまっとうである」という社会的規範に疑問を投げかける作品です。
- 主人公・古倉恵子は36歳未婚、コンビニのアルバイトを生きがいとする女性。
- 「普通」の生き方から外れた彼女が、社会の同調圧力と向き合う姿を描いています。
- 結婚や正社員であることが「正常」とされる価値観に対する批判的視点を持つ作品です。
この昭和から平成、64年の歳月を経てもなお、結婚せず子どもを持たない女性が生きづらさを感じる社会の現実を描いています。
キャリアとジェンダーの壁
しかし現代において、女性は家庭を守ったり、子供を育てたりする役割を期待される一方で、キャリアを築くことも期待されています。
私は医師です。幼少期から自立するように育てられ、父親の影響もあり医師となりました。
教育においては男女平等で、評価は試験の点数。公平に評価されてきたと感じています。
しかし、一度妊娠・出産・子育てのフェーズに直面すると、状況は一変します。
- キャリアブランク(出産、育児によるキャリアの中断)が避けられない。そのため、「専門医を取るまでは産まない方がいい」という教授や医局のプレッシャーが存在する。
- 育児とキャリアの両立の困難さ。留学をする医師はキャリアブランクを経験しない男性医師が大半。
- 「ママ女医」への偏見。権利を主張すると嫌われる、という現実。
女性のキャリアを応援する社会になりつつありますが、特に病院においてはまだまだジェンダー不平等は根強く残っています。
リプロダクティブライツ(生殖に関する権利)
今月は、前述したように
ロー対ウェイド判決をめぐる保守派とリベラル派の対立
経口中絶薬の普及を推進するNPO団体「PLAN C」
女性の権利やリプロダクティブライツの擁護に尽力したギンズバーグ判事の功績
について、熱心に学びました。
女性主体の避妊へのアクセスが限られており、費用も高額であること、中絶に対する制約があることは、依然として社会が男性中心であることを痛感させられます。
しかし、妊娠・出産・育児の負担を主に担うのはやはり女性であり、人生の自己決定権という観点からも、産むかどうかの選択は母親となる本人が決めるべきだと私は考えています。
女性の自己決定権が保障されると、社会はどう変わるか?
国連人口基金(UNFPA)は、
"A society where women can control their own bodies is healthier and more economically prosperous."
「女性が自らの身体をコントロールできる社会は、より健康で、経済的にも発展する」
と指摘しています。
☑︎望まない妊娠を防ぎ、心身の健康が守られる
☑︎教育やキャリアの選択肢が広がり、経済的な自立が可能になる
☑︎出産・育児のタイミングをコントロールでき、より良い環境で子どもを迎えられる
女性の権利が守られることは、個人の幸福だけでなく、社会全体の発展につながるのです。
私たちにできること
☑︎知ることから始める – 日本や世界のリプロダクティブライツの現状を学び、正しい知識を身につける。
☑︎主体的に人生を選択する – 結婚するかしないか、子どもを持つかどうか、どんなキャリアを築くか。自分自身にとって最善の選択ができるよう、考え、行動する。
Women's History Month は、過去の女性たちの闘いを振り返り、今私たちが何をすべきかを考える機会です。
次世代の女の子たちが、より自由に、自分らしく生きられる社会へ。
「女性の選択を尊重する社会」 を目指し、今できることから始めていきましょう!
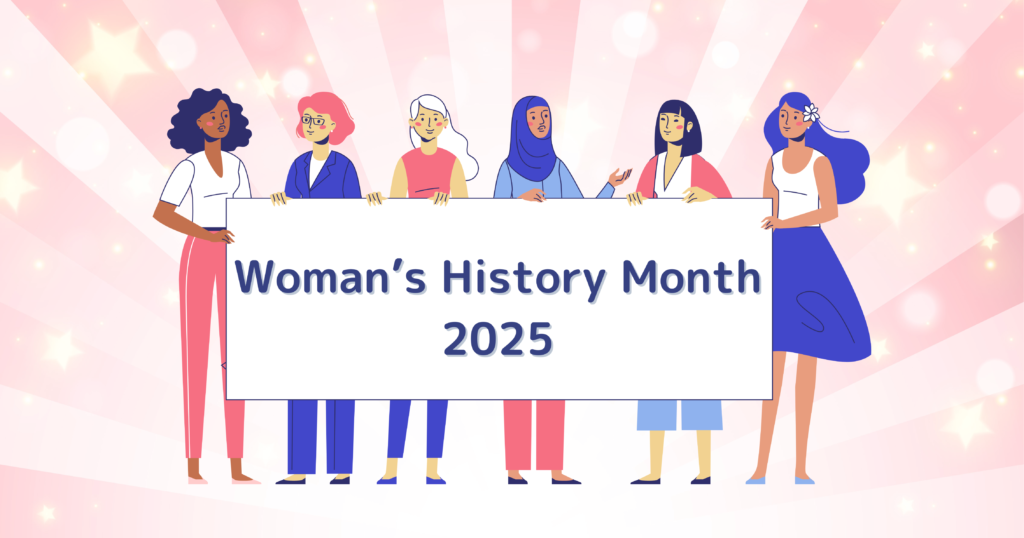
自分の人生を主体的に生きる
ライフキャリアプランを考える上で、ヒントになりそうなことがたくさん詰まったメール講座をご用意しています。

お興味のある方は、こちらのページをご覧ください。
Life Career Planning
いつの間にか人生100年と言われる時代になったけれど女性にとって変わらない事実があります。 それは、妊娠・出産にリミットがあること。 どんどん仕事がおもしろくなる20代後半から30代前半のキャリア形成期はまさに妊娠・出産 […]




